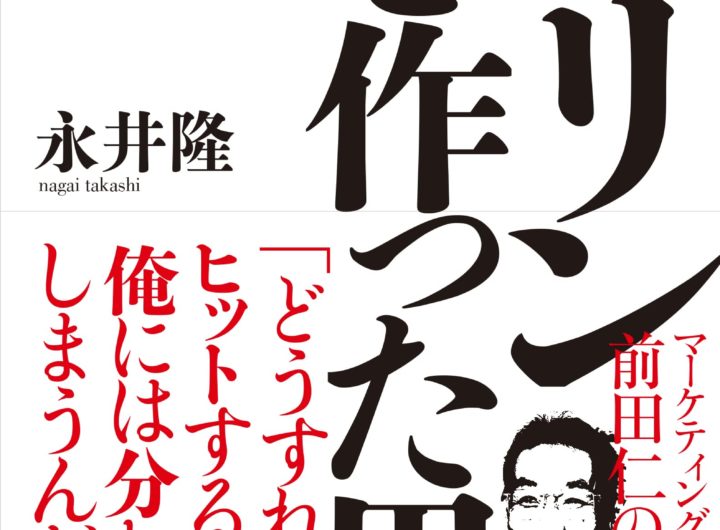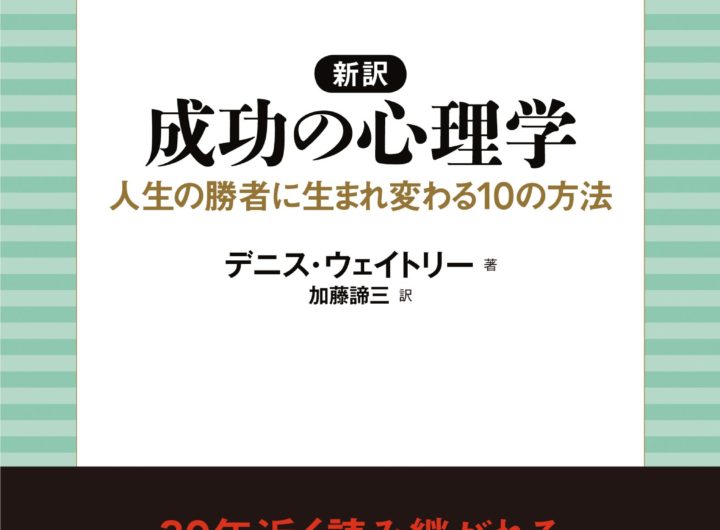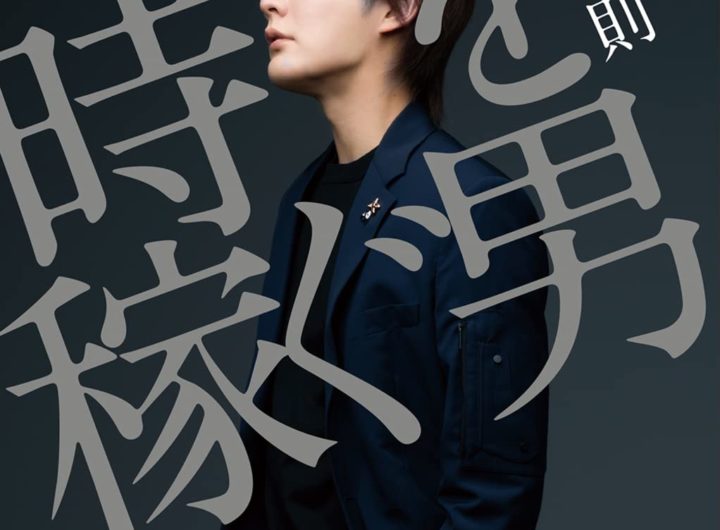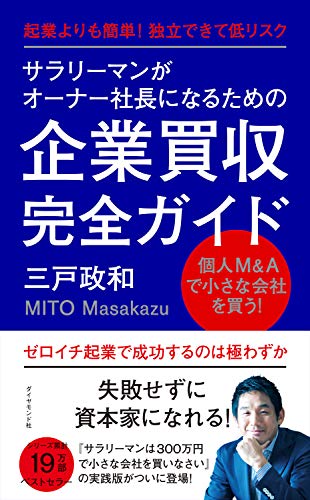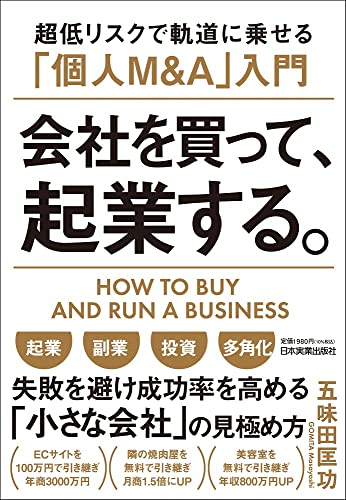サイバーエージェント藤田社長の起業家としてのスピリットが凝縮された本となります。
1998年にサイバーエージェントを設立し、2000年に東証マザーズに上場、同時に史上最年少上場社長になるなど、まさに絶好調!と、思いきや2001年にはインターネットバブルの崩壊による株価の下落と投資家からの冷たい視線を受けることになるなど、時代の荒波に揉まれまくっていた藤田社長。当社の低迷していた業績に終止符を打つべくメディア企業への転換を決意します。
当時はネットバブル崩壊後でもあったことから、投資家からはサイバーエージェントのメディア事業への先行投資に対する辛口コメントが多くあり、また社内の人間からも藤田社長の方針について疑問視されたりと孤独を感じる日々が続いていました。
今まで誰もやったことがないことって答えがない上に、奥行きも見えないから本当に不安になるんだろうな。と、当時の藤田社長の心境がひしひしと伝わる、そんな本でした。
これから起業を考えている方や、新しいことにチャレンジしようと考えている方にはとても刺激になる本だと思います。ちなみに私もめちゃくちゃ刺激されました。笑
藤田社長の学生時代から起業当初、そしてネットバブルと崩壊の局面については、『渋谷ではたらく社長の告白[新装版]』を是非読んでみてください。
(こちらも刺激強めです。笑)
飲みにケーションはチームの団結を高める
社内の活性化に非常に効果があったのが社内の飲み会を奨励したことであると記載があります。
しかもこの飲み会は翌日の午前休暇もセットでついており、本気で飲んでも問題ないように仕組みが確立されていました。
私も社会人になり、右も左も分からない中、上司やチームのみんなと初めてコミュニケーションを取ることができたのは、やはり社内の飲み会でした。
しかし、私の入社した時代の金融機関は、飲み会の頻度があまりに多過ぎて、しかも、多少上司が多めに支払してくれるにしても、当時の給与からはかなり痛い支払額でもあったことから、正直な話、めちゃ憂鬱でした。
もう勘弁してくれ。と内心思ってました。笑
藤田社長は若い頃から飲み会をよくやっていた経験から、このような飲み会の弱点を全て払拭したような制度を設けており、この環境だったら飲み会が楽しくなり、コミュニケーションも活発になるだろうなと思いました。
新規事業と撤退
新規で事業を始めると、取引先や関係者など、様々なしがらみができてしまうことから、どうしても撤退を先延ばしにしがちになると書かれています。
そこで藤田社長は、1年半で黒字化しない場合、もしくは赤字が設定した金額を下回ったら撤退と決めていたそうです。
ベンチャー企業のように、新規事業を常に追いかけ続ける企業は、この基準を作らないと資金が底をついてしまい、事業を継続し続けるとことができなくなるので、この基準を設けることは、ある意味、安全装置的な役割をしているように思います。
一方で、創業開始から一定期間の経った、例えばよく目にするような大企業においては、赤字の事業をなかなか撤退できていないように思うことが多々あります。
ベンチャー企業と違いお金もあるので、すぐに決めなくとも大丈夫ですし、その事業で抱えている人員も多く、その決断を下せないのでしょうかね。とか考えてしまいました。笑
ソニーのように、黒字の事業でも、将来の企業の方向性や、マーケットの見通しが芳しくない事業を、バンバン売却するようなことまでする必要はないですが、赤字や採算マイナスの事業についてはしっかりと見定めて決断していくことの重要性をこの新規事業の撤退ルールで感じました。
堀江社長から色々な刺激を受け続ける
『渋谷ではたらく社長の告白[新装版]』に引続き、本書でも堀江社長は度々登場します。ここではM&Aによりどんどん加速していくライブドアに嫉妬する藤田社長から始まり、堀江社長の逮捕によるライブドア事件をみてショックを受け、堀江社長の出所後には二人きりの部屋で寿司を食べた話までが書かれています。
当時、サイバーエージェントはアメブロを流行らせるために必死でした。そのブログサービスの可能性に注目していたのは、藤田社長の他には、堀江社長だけだったとも記載されています。
堀江社長を初めて知ったのは、プロ野球球団を買収すると名乗りを上げたときである人は多くいるかと思います。あの一連の騒動では、結果的に堀江社長は球団のオーナーになることはありませんでしたが、堀江社長は「名乗りを上げるのはただ(無料)、これは発見だったよ。」と言っていたと記載があったのが、私としてはとても印象的でした。
まさに、行動したものにしか得られないであろう発見を、若干31歳にてして経験し、それをその後続けていったというのはなんとも恐ろしい。
自分自身が新たに始めたサービスのヘビーユーザーになること
新しいサービスやデバイスを自分で使って試さないのは、ネット業界の経営者としては失格であると記載されています。
本当にいいサービスを提供するには、自分で使ってみて、感じて、それを改善していく必要があり、その改善についても、これまでは外部に委託をしていたのでは限界があり、自社で開発も手掛けることにしたという内容を読んだとき、成功する人の執念はやはり人並みではないなと思い知らされました。
KPI(業績評価)が会社の行く末を決める
これまでのサイバーエージェントでは、収益にフォーカスしたKIPを設定していたことから、サービスのクオリティーに迷いがあるような状態が続いていました。
そのKPIを収益からページビュー数へとシフトさせ、”どうすれば稼げるか。から“どうすればサービスを使ってくれるか”に切替えた結果、これまで伸び悩んでいたページビューを格段に伸ばすことに成功し、最終的に黒字化まで一気に駆け抜けることができました。
私はこれまで様々な企業のKPIを見てきましたが、KPIの設定が業績を左右することを改めて実感することができました。
不用意に多くのKPIを設定したり、本質的な意味をなさないKPIを設定するのはやめましょう。
新しいことをする上で、どのように信頼を勝ち取るか
会社のトップを走る経営者として、新しいことを初めることによる様々な方向からのプレッシャーは想像を超えたものがあると思います。
そんな中、信頼を勝ち取る方法はただ一つ、“言い続けたことが現実になること”であると記載されています。
“すべての創造はたった1人の熱狂から始まる”。新しいことを生み出すのは1人の孤独の熱狂であるという文面は、私に刺激しか与えませんでした。笑
最後に
未知の世界に飛び込む勇気と、飛び込んでからの忍耐力は、新しいことに取組んだことのある人しか知ることのできない、とても刺激的で、また人間力を成長させる絶好の機会であると感じました。
俺もなんか始めてみようかな。